こんにちは。愛知県豊橋市にある三宅歯科医院です。
お子さまの歯みがきをしているときに「また虫歯ができた」と感じたことはありませんか。歯みがきを丁寧にしていても、虫歯になりやすい子どもとそうでない子どもがいます。
虫歯は放置すると痛みが出るだけでなく、永久歯の健康にも影響を及ぼすため、早期の予防と正しいケアがとても大切です。
今回は、虫歯になりやすい子どもの特徴や虫歯の原因、そして今日から実践できる効果的な予防方法についてわかりやすく解説します。お子さまの虫歯についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
虫歯になりやすい子どもの特徴

虫歯になりやすい子どもと、そうでない子どもにはいくつかの違いがあります。ここでは、虫歯になりやすい子どもの特徴をご紹介します。
歯の質が弱い子ども
虫歯になりやすい子どもの大きな特徴のひとつが、歯の質が弱いことです。歯の性質は個人差があり、同じ環境でも虫歯になりやすい子とそうでない子がいるのです。
また、乳歯は永久歯に比べて歯の表面のエナメル質が薄く、酸に対する抵抗力が低いため、虫歯菌が出す酸によって溶けやすい構造をしています。加えて、もともとエナメル質が薄い場合や、歯質が柔らかい場合は、さらに虫歯になりやすいといえるでしょう。
唾液の量が少ない子ども
唾液は、虫歯の原因となる細菌を洗い流し、口の中をきれいに保つ重要な役割を持っています。唾液の分泌量が少ない子どもや、粘度の高い唾液の子どもは、唾液による自浄作用が低下するため虫歯のリスクが高まります。
間食が多い子ども
おやつやジュースの回数が多い子どもも、虫歯になりやすいと言えるでしょう。砂糖を含む食品を頻繁に口にすると、口の中が酸性状態に傾く時間が長くなり、歯の再石灰化が追いつかなくなります。
特に、スポーツドリンクや乳酸菌飲料など一見健康そうな飲み物にも、糖分が多く含まれています。知らず知らずのうちに、虫歯になりやすい口内環境になっていることもあるのです。
子どもの虫歯の原因

虫歯は、ミュータンス菌などの細菌が口の中で繁殖することによって引き起こされます。口の中にある糖分をエサにして、細菌は酸を作り出します。その酸が、歯の表面を溶かして虫歯を発生させるのです。
子どもは一度に食べられる食事の量が少ないため、間食も利用して栄養を取ることが推奨されています。
しかし、食事の回数が増えると、食べかすが溜まりやすくなり、虫歯のリスクが高まります。さらに、子どもは歯みがきが不十分なことが多く、歯の表面だけでなく食べかすの溜まりやすい奥歯の溝や歯と歯の間、歯ぐきの部分に虫歯が発生しやすいです。
子どもの虫歯をそのままにするリスク

子どもの乳歯が虫歯になっても、永久歯に生え変わるからと放置する方もいるかもしれません。
しかし、実際にはさまざまなリスクがあるため治療しなければなりません。以下で、虫歯をそのままにするリスクについてくわしく解説します。
痛みや感染が広がる
乳歯の虫歯を放置すると、虫歯は歯の内部まで進行し、強い痛みを引き起こします。さらに進行すると、歯の根の部分にまで炎症が及び、膿がたまって腫れたり、発熱を伴ったりすることもあります。
子どもの場合、痛みをうまく訴えられず、気づいたときには虫歯が進行していることも珍しくありません。炎症が広がると、あごの骨や周囲の組織にも影響を及ぼす恐れがあります。
食事や発音への影響
虫歯が痛むと、食べ物をしっかり噛めなくなり、やわらかいものばかりを好むようになることもあるでしょう。これにより、あごの発達や筋力の発育が遅れ、かみ合わせにも悪影響を及ぼす可能性があるのです。
また、前歯の虫歯や虫歯による欠損は、発音に支障をきたすこともあります。特に、さ行やた行の発音が不明瞭になるケースが多く、言葉の発達にも影響する可能性があります。
永久歯への悪影響
乳歯の下には、将来生えてくる永久歯の芽が存在します。虫歯を放置すると、炎症が歯茎の下の永久歯にまで及び、永久歯の形成不全や変色、まっすぐ生えてこないといった問題を引き起こすことがあるのです。
また、乳歯が早期に抜け落ちると、隣の歯が傾いたり倒れたりしてスペースがなくなり、永久歯の歯並びが乱れる原因にもなります。
心理的な影響が出る可能性がある
前歯などの目立つ部分に虫歯ができ、変色すると笑顔を見せることをためらったり、人前で話すことを嫌がったりする子どももいます。周囲とのコミュニケーションに消極的になり、人間関係に悪い影響を及ぼすかもしれません。
歯の健康は、単に口の中だけでなく、子どもの自信や社会性にも関わる大切な要素なのです。
子どもの虫歯の予防方法

虫歯ができても早期に治療すれば、大きな問題になることはほとんどありません。
しかし、治療には時間も費用もかかり、子ども自身にも負担がかかるでしょう。虫歯は予防ができる病気のため、予防するのが理想です。以下で、虫歯の予防方法をくわしく解説します。
毎日の正しい歯みがき習慣
虫歯予防の基本は、やはり毎日の歯みがきです。子ども自身に歯みがきの習慣を身につけさせるとともに、小学校低学年までは保護者の仕上げみがきが欠かせません。
さらに、生え変わりが完了してもしばらくは仕上げ磨きを続けることが理想です。歯ブラシは子どもの口の大きさに合ったものを選び、毛先が広がる前に交換することが大切です。
食生活の見直しと間食のコントロール
食生活の改善も虫歯予防に欠かせません。砂糖を多く含むお菓子やジュースはなるべく控え、間食の回数を1日1〜2回程度に、時間を決めるようにしましょう。
だらだら食べを防ぐことで、口の中が長時間酸性になることを避けられます。また、おやつには、ナッツ類などのしっかりと噛む必要があるものを取り入れることで、唾液の分泌を促す効果があります。
水分補給には砂糖を含まない水やお茶を選ぶようにすることも効果的です。
フッ素の活用
乳歯や生えたばかりの永久歯は特に虫歯になりやすいため、定期的なフッ素塗布が効果的です。歯科医院で行うフッ素塗布は、歯のエナメル質を強化し、虫歯菌が出す酸に溶けにくい歯をつくる予防法です。
また、自宅での歯磨きにもフッ素入り歯みがき剤を取り入れることで、歯の再石灰化を目指せるでしょう。
定期検診で早期発見・早期治療を行う
歯科医院での定期検診は、虫歯を未然に防ぐ最も確実な方法の一つです。数カ月に一度のペースで受診し、虫歯の有無などをチェックしてもらいましょう。
歯科医院では、ブラッシング指導を受けることもできます。子ども自身への指導はもちろん、仕上げ磨きの方法も定期的に見直すと良いでしょう。
そのほか、歯科医師や歯科衛生士によるプロのクリーニングは、自宅では落としきれないプラークや歯石を除去し、口の中を清潔に保ちます。さらに、生活習慣や食事内容のアドバイスを受けることで、家庭でもより効果的な予防が期待できます。
保護者の口腔ケアと家庭での意識づけ
子どもの虫歯を放置することは、家庭全体の口腔ケア意識の低下にもつながるでしょう。お子さまの虫歯をきっかけに、家族全員で歯みがき習慣や定期検診を見直すことが、健康な口腔環境を保つうえで重要です。
子どもの前で保護者が歯みがきを行うなど、家庭全体で口腔ケアの意識を高めることも効果的です。親子で楽しく歯みがきを行う習慣を作ることで、自然と虫歯予防の意識が育まれます。
まとめ

虫歯になりやすい子どもには、歯の質や唾液量、生活習慣など、いくつかの特徴があります。乳歯は永久歯よりも虫歯になりやすく、進行も早いため、日々のケアと早期対応がとても重要です。
虫歯を放置すると痛みや感染が広がるだけでなく、永久歯の発育や歯並び、さらには発音や食事の発達にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、毎日の歯みがきに加えて、フッ素塗布や定期検診などの予防的なケアを積極的に取り入れることが大切です。
小さな頃から正しいケア習慣を身につけることで、一生自分の歯で食べる力を守っていくことができます。
お子さまの虫歯予防を検討されている方は、愛知県豊橋市にある三宅歯科医院にお気軽にご相談ください。
当院では、予防歯科とマウスピース矯正に力を入れています。虫歯・歯周病治療やホワイトニング、入れ歯治療、インプラント治療なども行っています。当院のホームページはこちら、WEB予約も受け付けておりますのでご覧ください。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
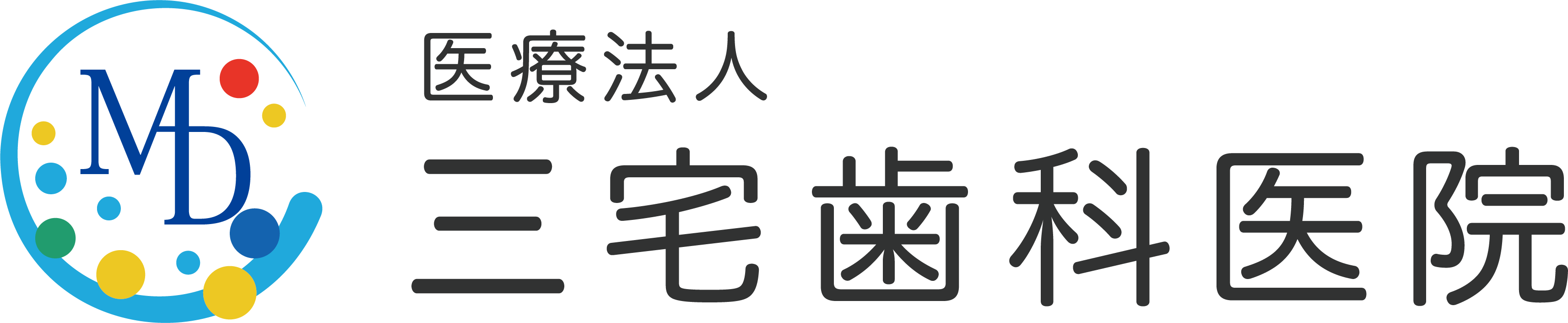





 お電話
お電話