こんにちは。愛知県豊橋市にある三宅歯科医院です。
「タバコを吸っていると歯周病になりやすいと聞いたけど本当か」「喫煙が歯茎に与える影響について詳しく知りたい」と疑問を持つ方は多いでしょう。実際に、喫煙は歯周病の発症リスクを高め、その進行を著しく促進させる重要な危険因子として知られています。
この記事では、喫煙と歯周病の深い関係について解説し、禁煙の重要性や歯周病予防のための具体的な対策について説明します。この記事を参考に、喫煙が歯の健康に与える影響を正しく理解し、適切な予防策を実践してください。
目次
歯周病とは

歯周病は、歯を支える歯茎や歯槽骨などの歯周組織に炎症が起こる疾患です。まずは発症する原因や症状について説明します。
歯周病の原因
歯周病の主な原因は、口の中に蓄積された歯垢に含まれる細菌です。歯垢は食べ物の残りカスや唾液の成分、細菌が混ざり合って形成される粘着性の物質で、適切な歯磨きが行われないと歯と歯茎の境目に蓄積していきます。
この歯垢に含まれる細菌が毒素を産生し、歯茎に炎症を引き起こすことで歯周病が発症します。
歯垢が長期間放置されると、唾液中のミネラル成分と結合して歯石という硬い物質に変化します。歯石は歯ブラシでは除去できず表面はデコボコしているため、さらに多くの細菌が付着しやすくなり、歯周病の進行を促進させる悪循環を生み出します。
歯周病の症状と進行段階
歯周病は進行度によって大きく2つの段階に分けられます。
初期段階の歯肉炎では、歯茎が赤く腫れ、歯磨きの際に出血しやすくなります。この段階では歯を支える骨には影響がないため、適切な治療により完全に回復することが可能です。
しかし、対処されないまま放置すると、歯周炎へと進行します。
歯周炎では歯茎の炎症が深部に及び、歯と歯茎の間に歯周ポケットと呼ばれる深い溝が形成されます。歯周ポケットの中でさらに細菌が繁殖しやすい環境となり、歯を支える歯槽骨が徐々に溶けて破壊され始めます。
歯がグラグラと動くようになり、さらに進行すると歯が抜け落ちる可能性が高くなります。
歯周病は初期段階では痛みを感じにくいため、自覚症状がないまま進行することが多いのが特徴です。そのため、定期的な歯科検診による早期発見と適切な治療が極めて重要になります。
歯周病と喫煙の関係

喫煙は、歯周病を悪化させる最も大きなリスク因子の一つです。ここでは、具体的に喫煙が歯周病にどのような影響を与えるのかについて見ていきましょう。
喫煙が歯周病に与える悪影響
タバコの煙には、ニコチン、タール、一酸化炭素など、200種類以上の有害物質が含まれています。これらの物質が、お口の中に直接的・間接的に作用し、歯周病の進行を加速させます。
血行不良を引き起こす
ニコチンには血管を収縮させる作用があります。これにより、歯茎の毛細血管が収縮し、歯茎への血液の流れが悪くなります。歯茎への血液供給が滞ると、歯周組織に必要な酸素や栄養素が十分に届かなくなり、組織の抵抗力が低下します。
また、炎症が起きても白血球などの免疫細胞が十分に集まりにくくなるため、歯周病菌と戦う力が弱まります。その結果、歯周病の進行が早まるだけでなく、歯周病が発症しても初期の症状である歯茎の出血が起こりにくくなるのです。
そのため、患者さま自身が歯周病の進行に気づきにくくなるという問題も生じます。
免疫機能の低下
タバコに含まれる有害物質は、体の免疫システムにも悪影響を与えます。特に、細菌と戦う役割を持つ白血球の一種である好中球の機能が低下することが知られています。
好中球は歯周病菌を貪食し、増殖を抑える重要な役割を担っていますが、喫煙によってその働きが鈍くなるため、歯周病菌がより活発に活動しやすくなります。結果として、炎症が広がりやすくなり、歯周組織の破壊が加速されます。
傷の治癒を遅らせる
喫煙は、体の組織の修復能力を低下させます。
歯周病治療では、歯周ポケット内の細菌を除去しますが、その後の歯茎の回復や再生が喫煙者では著しく遅れる傾向にあります。これは、ニコチンによる血行不良や、線維芽細胞という組織の再生に関わる細胞の機能低下などが原因と考えられます。
そのため、治療の効果が十分に得られにくかったり、再発しやすくなったりすることがあります。
唾液の質と量の変化
喫煙は唾液の分泌量や質にも影響を与えることがあります。
唾液には、お口の中を洗い流す自浄作用や、細菌の増殖を抑える抗菌作用、歯を再石灰化させる働きなど、重要な役割があります。喫煙によって唾液の分泌が抑制されるとお口の中が乾燥しやすくなり、細菌が洗い流されにくくなるため、歯周病だけでなく虫歯のリスクも高まります。
喫煙による歯周病の具体的な影響
上述したような喫煙が与える悪影響により、喫煙者は非喫煙者の2~8倍、歯周病にかかりやすいとされています。特に、1日の喫煙本数が多いほど、リスクは高まります。
また、喫煙者の方が非喫煙者よりも歯を支える骨の破壊が早く進行するとされています。より深い歯周ポケットや広範囲な骨の破壊が見られることが多く、重度の歯周病になりやすい傾向があるのです。
さらに、歯周病治療や外科的な治療を行っても、非喫煙者に比べて治療後の歯周組織の改善が乏しく、再発しやすいことが知られています。
このように、喫煙は歯周病の発症から進行、治療効果、そしてその後の予後に至るまで、あらゆる側面に悪影響を及ぼします。ご自身の歯の健康を真剣に考えるのであれば、喫煙習慣の見直しは避けて通れない重要な課題と言えるでしょう。
歯周病の進行を抑えるためには禁煙が必要?

歯周病の進行を抑え、治療の効果を最大限に引き出すためには、禁煙が極めて重要です。喫煙が歯周病に与える悪影響は非常に大きいですが、禁煙すればこれらの負の連鎖を断ち切ることができます。
禁煙がもたらす歯周病への好影響
禁煙すると、数日~数週間で歯茎の血行が改善され始めます。これにより、歯周組織への酸素や栄養の供給が回復し、免疫細胞が活発に働くことができるようになります。
また、低下していた免疫機能も徐々に回復し、白血球の働きが正常に戻ることで歯周病菌への抵抗力が高まり、炎症の抑制に繋がります。さらに、お口の環境が改善されることで、歯周病菌の増殖が抑えられ、細菌のバランスが良好な状態へと変化します。
治療効果も向上しやすくなり、禁煙することで、スケーリングやルートプレーニングといった基本的な歯周病治療の効果が格段に上がります。
禁煙の重要性
禁煙すれば今までのダメージが全て元に戻るというわけではありません。
しかし、歯周病の進行を食い止め、これ以上の悪化を防ぐためには、禁煙が最も効果的な方法であることは間違いありません。歯科医院での治療は重要ですが、喫煙を続ける限り、その治療効果は限定的なものになってしまうでしょう。
禁煙は決して簡単なことではありませんが、ご自身の歯を守り、将来にわたってお口の健康を維持するためには、避けて通れない道です。禁煙を成功させるためには、強い意志に加え、周囲のサポートや禁煙補助剤の活用も有効です。
かかりつけの歯科医師や内科医に相談し、禁煙外来などを利用することも検討してみてください。
歯周病予防のために禁煙以外で大切なこと

禁煙は非常に大切ですが、それだけでは歯周病を防ぐには不十分です。日常的な口腔ケアや生活習慣の見直しも必要です。
正しいブラッシングと定期的な歯科検診
毎日の歯磨きを丁寧に行い、歯と歯茎の境目をしっかりと磨くことが大切です。力任せに磨くのではなく、歯ブラシを細かく動かしながら歯垢を除去します。歯ブラシでは届きにくい歯間部の汚れは、歯間ブラシやデンタルフロスも使用して清掃しましょう。
さらに、歯科医院での定期的なクリーニングと検診を受けることで、問題の早期発見と予防が可能になります。
食生活の見直しとストレス管理も重要
ビタミンCなどの栄養素が不足すると、歯茎の健康にも悪影響が出ます。バランスの取れた食事を心がけましょう。また、ストレスが免疫力を下げることも知られているため、リラックスできる時間を作ることも歯周病予防に役立ちます。
唾液の分泌を促す習慣づけ
唾液には、細菌の増殖を抑える自浄作用があります。ガムを噛んだり、水分補給を心がけたりすることで、お口の中を清潔に保てます。
まとめ

喫煙は歯周病のリスクを高め、歯茎の血流や免疫機能を低下させることで、歯周組織の状態悪化を招きます。その結果、歯周病の進行が早まり、治療の効果も十分に得られにくくなります。
しかし、禁煙することで、歯茎の回復力が高まり、歯周病の予防・治療効果を格段に高められます。
歯を守るためには、喫煙習慣を見直すだけでなく、日々の口腔ケアや生活習慣全体を整えることが欠かせません。歯茎の腫れや出血などのサインに気づいたら、早めに歯科医院を受診しましょう。
ご自身の健康のためにも、今日からできることを一つずつ始めてみてください。
歯周病の予防・改善を検討されている方は、愛知県豊橋市にある三宅歯科医院にお気軽にご相談ください。
当院では、予防歯科とマウスピース矯正に力を入れています。虫歯・歯周病治療やホワイトニング、入れ歯治療、インプラント治療なども行っています。当院のホームページはこちら、WEB予約も受け付けておりますのでご覧ください。
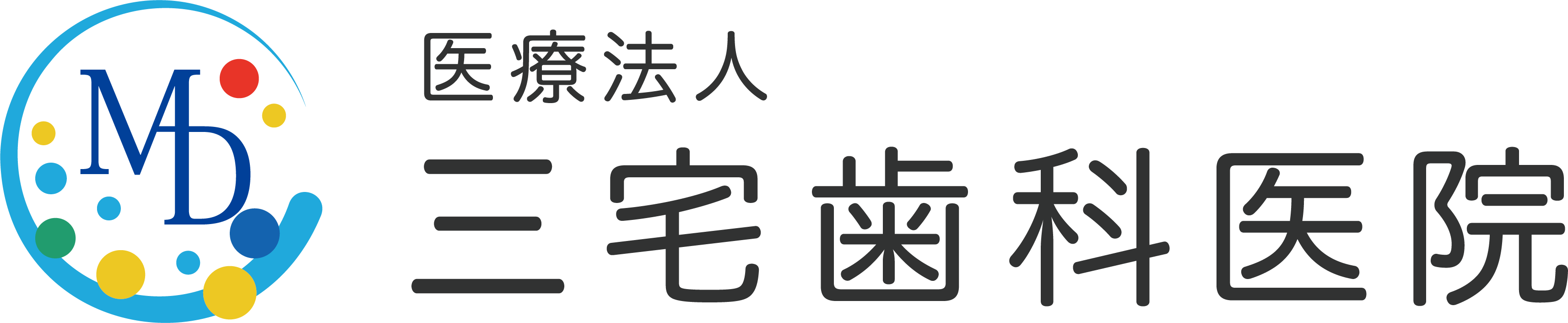






 お電話
お電話